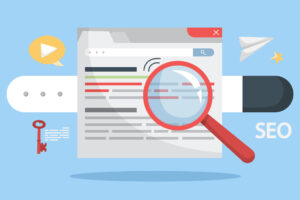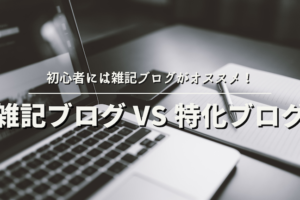はじめまして。エンジニアのMinatoです。
今回は「SEOを成功させる、初心者のためのWebライティング」ということで、以下のようなお悩みを持たれてる方に向けて本記事を書いています。
- 「ブログ、Webサイトを始めたけど、どのように記事を書いたらいいかわからない」
- 「記事を書いても成果がでずに困っている」
- 「そもそもSEOってなに?」
SEOと聞くとなんだか難しいそうで、「Webマーケティングの専門家がやることでしょ」と思いがちですが、決してそうではありません。
重要なのは「読者のことを最優先に考えたコンテンツを作成する」ということです。
今回は、「読者のことを最優先に考えたコンテンツを作成する」上で、誰にでも実践できるWebライティングのテクニックをご紹介したいと思います。
本記事をご一読いただくことで、以下の知識が身に付きます。
- SEOとは何か!
- SEOを成功させるためのWebライティングとはどのようなものか!
- ブログ、Webサイトで成果を出すために、どのように文章を書けば良いか!
本記事を書くにあたって、Webマーケティング書籍のベストセラーである以下の書籍を参考書籍とさせていただきました。
こちらの内容をベースに仕事や家事で忙しく、1からSEOやWebライティングについて勉強する時間がないという方に向け、要点をギュッとまとめて解説していきたいと思います。
沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—
「沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—」を参考書籍とした理由は以下の通りです。
- ストーリー仕立てで初心者にも分かりやすい
- Webマーケティング関連の本でロングセラーである
- Webライティングの実践的なテクニックが網羅されている
SEOを成功させる、初心者のためのWebライティング
目次
結論からお伝えすると、SEOを成功させる文章を書くためには、以下のポイントを考慮して記事を書く必要があります。
- 専門性、信頼性、網羅性の3つの要素を意識して記事を書く
- 読みやすく、分かりやすい文章を書くためのポイントをおさえて書く
- USPをわかりやすく伝える
この3点をしっかり考慮して記事を書くことで、SEOの効果を高め、Googleの検索結果の上位に表示されるようになります。
本記事では、上記の3点について、順をおってご説明していきます。
その前に、そもそもSEOとは何なのかについて、簡単にご説明しておきます。
Webライティングについての具体的な解説は「SEOを成功させるWebライティングを行うために重視すべき3つの要素」以降に記載していますので、「SEOが何かはもう知っているよ」という方は、読み飛ばしていたただいて問題ありません。
そもそもSEOとは何なのか?
SEOとはSearch Engine Optimizationの略で、日本語にすると検索エンジン最適化という意味になります。
「いきなり検索エンジン最適化と言われてもなんのことかわからない」ですよね。
簡単に説明すると検索エンジンからサイトに訪れる人を増やして、Webサイトの成果を向上させる施作のこと全般をいいます。
つまり、Googleから評価され、検索結果の上位に表示されるようにするために、Webサイトの構造やコンテンツの内容をチューニングすることをSEOといいます。
Googleの検索結果の上位に表示されれば、多くのユーザーにあなたのコンテンツが見てもらえるようになるので、商品の売り上げUPや広告収入の増加につながります。
ここまででなんとなく本記事の結論が見えたと思いませんか?
そうです、あなたの予測の通り、「SEOを成功させ、ブログやWebサイトで成果を出すためのWebライティング」とは、Googleから評価されるコンテンツを書くことということです。
補足: なぜGoogleなのか?
検索エンジンには、Google、Bing、Yahoo!、Baiduなど、様々な種類があります。
しかし、日本で主要な検索エンジンは、GoogleとYahoo!になります。
さらに、現在、日本のYahooはGoogleの検索エンジンを採用しており、Googleのシェアは実質90%を超えています。
よって、Googleのみ考慮しておけば問題ないと言えます。
なぜSEOを意識したWebライティングが重要なのか?
「なぜSEOを意識したWebライティングが重要なのか?」
その理由は、SEOを意識したWebライティングを行うことで、検索結果の順位が上がり、サイトへのアクセスが増えるからです。
アクセス数を増やすだけなら、「SNSで拡散すれば良いのでは?」と思われるかもしれません。
確かに、SNSで拡散することも非常に有効な手段であり、重要だといえます。
しかし、SEOを行い、検索結果で上位に表示させることには、SNSにはない大きなメリットがあります。
その一つは、検索結果の上位に表示することが「プル型のアクセス」を生むという点です。
Google検索のようにユーザーが自分から積極的に情報を取得しようとするアクセスを「プル型のアクセス」と呼びます。
一方、SNSのように一方的に情報を発信し、それを発見した人に見てもらうのを「プッシュ型のアクセス」と呼びます。
検索エンジンを使うユーザーは自分の悩みや質問を解決する「答え」を積極的に求めていると言えます。
よって、自分の興味のあるコンテンツが検索結果に表示された場合は積極的にアクセスしてくれるので、SNSからのアクセスより成果につながりやすことが多いです。
例えば、「ダイエット 簡単」と調べる人は、簡単に実践できるダイエット方法を知りたいと考えています。
よって、簡単にダイエットができる健康食品やダイエット方法が紹介された記事を読み、さらに関連する商品を購入する可能性が高いといえます。
二つ目のメリットは、「継続してアクセスを得ることができる」という点です。
SNSでは、基本的に時系列に情報が流れていきますので、古くなった投稿から多くのアクセスにつながることはまれです。
一方、Google検索では、上位に表示されている限り、長期的にアクセスを生むことができます。
Googleから評価されるために重要なこと
Googleから評価されるコンテンツを書くために、まず、Googleが何を重要視しているかを考えてみましょう。
結論からお伝えするとGoogleは「ユーザーの利便性を最優先に考えること」を重要視しています。
このことはGoogleの経営理念である「Google が掲げる 10 の事実」からも伺い知ることができます。
1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。
Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えています。新しいウェブブラウザを開発するときも、トップページの外観に手を加えるときも、Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。Google のトップページはインターフェースが明快で、ページは瞬時に読み込まれます。金銭と引き換えに検索結果の順位を操作することは一切ありません。広告は、広告であることを明記したうえで、関連性の高い情報を邪魔にならない形で提示します。新しいツールやアプリケーションを開発するときも、もっと違う作りならよかったのに、という思いをユーザーに抱かせない、完成度の高いデザインを目指しています。
Google が掲げる 10 の事実
https://www.google.com/about/philosophy.html?hl=ja
また、Googleが提供している「ウェブマスター向けガイドライン」にも以下のように記されています。
基本方針
・検索エンジンではなく、ユーザーの利便性を最優先に考慮してページを作成する。
ウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)
・ユーザーをだますようなことをしない。
・検索エンジンでの掲載位置を上げるための不正行為をしない。ランクを競っているサイトや Google 社員に対して自分が行った対策を説明するときに、やましい点がないかどうかが判断の目安です。その他にも、ユーザーにとって役立つかどうか、検索エンジンがなくても同じことをするかどうか、などのポイントを確認してみてください。
・どうすれば自分のウェブサイトが独自性や、価値、魅力のあるサイトと言えるようになるかを考えてみる。同分野の他のサイトとの差別化を図ります。
https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/webmaster-guidelines?hl=ja
上に書かれていることは、決して綺麗ごとではなく、Googleの本心です。
これは、Googleのビジネスモデルを考えてみても分かります。
Googleは広告収入で利益をあげている企業です。よって、Googleを利用するユーザーが増えれば増えるほど、儲かる仕組みになっています。
そのため、創業当時からユーザーの利便性を最優先に考え、ユーザーを増やすために努めているのです。
- Googleが便利になるほどGoogleを利用するユーザーが増える
- 検索結果に表示される広告がより多くのユーザーの目に触れる
- 広告をクリックするユーザーが増える
- 広告収入が増える
Google検索は上記のような、ビジネスモデルになっています。
では、ユーザーの利便性を最優先に考えて作成したコンテンツとはどのようなコンテンツでしょうか。
それは以下を満たすコンテンツと言えます。
- 検索ユーザーが今まさに抱えている「悩み」、「質問」に対して、「的確な答え」を返しているコンテンツ
- 「検索意図」にあったコンテンツ
- ユーザーの抱えている「悩み」、「質問」に対して、網羅的に答えを返している
- 同じ情報を扱っているサイトよりも、素早く答えが分かるコンテンツ
- 同じ情報を扱っているサイトよりも、みやすく、分かりやすいコンテンツ
- 同じ情報を扱っているサイトよりも、信頼できるコンテンツ
- 同じ情報を扱っているサイトよりも、情報が新しいコンテンツ
少し前置きが長くなりましたが、ここからはGoogleから評価されるコンテンツを書くために重要なポイント3点について、順をおってご説明していきます。
- 専門性、信頼性、網羅性の3つの要素を意識して記事を書く
- 読みやすく、分かりやすい文章を書くためのポイントをおさえて書く
- USPをわかりやすく伝える
SEOを成功させるWebライティングを行うために重視すべき3つの要素
専門性
誰でも知っているような当たり前なことを記事に書いてもGoogleからは評価されません。
Googleから評価されるコンテンツには「専門性」が求められます。
専門性のあるコンテンツとは、専門的な知識に裏付けされた、ユーザーにとって価値のある情報のことです。
例えば、私はエンジニアとして5年以上の経験があり、今までに様々なWebサイトやアプリケーションの開発にたずさわってきました。
よって、一般の方と比較するとITやプログラミングに関して専門性があるといえます。
そこで、プログラミングやITに関する記事を書くことで、これからプログラミングを学びたいという方に専門性のある情報を提供できることになります。
あなたが料理人であれば、料理に関する専門性があるので、料理に関する記事を書けば、ユーザーに専門性の高い情報を提供できますし、あなたが医師や看護師であれば医療に関する専門性があるので、医療に関する記事を書くことでユーザーに専門性の高い情報を提供できます。
しかし、「私は何かの専門家ではないし、専門性の高い記事なんて書けない」と思われる方もいらっしゃると思います。
そう思われる方も安心してください。専門性の高い記事を書くために、必ずしも職業として何らかの専門家である必要はありません。
私は、専門家でなくとも専門性の高い記事を書くために以下の方法が有効だと考えています。
- 今までの人生経験から得た、読者にとって価値のある情報について書く
- 多くの専門家の知識や意見を分かりやすくまとめて記事を書く
まず、1つ目の「今までの人生経験から得た、読者にとって価値のある情報について書く」についてご説明します。
例えば、あなたが過去に体型にコンプレックスを抱いていて、苦労してダイエットを成功させたという経験を持っていたとします。
きっとあなたは多くの時間をかけ、ダイエットに効果のある食事について調べたり、ダイエットに効果のある運動について調べたはずです。
そして、調べた方法を実践することで、見事にダイエットを成功させたという実績があります。
仮にあなたがスポーツトレーナーのような職業でなくとも、ダイエットという目的を達成した実績に裏付けされたあなたの知識は、ユーザーにとって価値のある専門性の高い情報となるといえます。
次に「多くの専門家の知識や意見を分かりやすくまとめて記事を書く」という点についてご説明します。
「多くの専門家の知識や意見を分かりやすくまとめて記事を書く」とは、書籍や論文など専門家が提供している知識を分かりやすく、噛み砕いて読者に伝えるということです。
書籍や論文に書かれていることはその分野の専門家が多くの時間を費やして生み出した非常に専門性と信頼性の高い情報です。
一方、専門家が書いた文章というのは、必ずしも読者にとって分かりやすいものとは限りません。むしろ、難解な専門用語が飛びかい、専門家どうしでしかわからないような情報であることが多いです。
そこで、あなたがしっかりと専門家が書いた文章の内容を理解し、読者にとって分かりやすい内容に変換することで新たな価値のある専門性の高い情報に生まれ変わるのです。
本記事で私が行っていることも、このパターンにあたるといえます。
私はエンジニアとして、日々仕事をしていますので、以前よりSEOについて基本的な知識は持っていました。
しかし、あくまでエンジニアであって、Webマーケッターではないので、職業的にはSEOやWebライティングの専門家ではありません。
そこで、参考書籍である「沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—」と作者の知識を借りて、専門性と信頼性を担保した記事に仕上げています。
信頼性
次に重要な要素は「信頼性」です。
「信頼性」を確保するためには、以下の2点が重要となります。
- どのような人が書いているか、なぜこの記事を書いているのかがはっきりしている
- 読者の「悩み」や「質問」に対する「答え」が、正しい根拠に基づいている
どのような人が書いているのか、どのような目的で記事を書いているのかを明らかにすることで、読者の信頼を得ることができます。
本記事を例にすると、現役のエンジニアである、わたしMinatoが書いています。
そして、エンジニアとしてSEOについて一定の知識はあったものの、システム的なSEO対策の知識のみで、実際にどのようにブログ記事を書くべきなのかわからないという悩みを抱えていました。
そこで、改めてWebライティングについて学び、得た知識を同じような悩みを持つ方に共有して、少しでも手助けになればと思い、本記事を書いております。
読者の「悩み」や「質問」に対する「答え」が、正しい根拠に基づいているという点については、文章が論理的に破綻していないこと、そして、その根拠が正しい情報に基づいているということが重要です。
どんなに思いの込めた記事であっても、論理的に破綻している内容であれば、読者に伝わりません。
そして、正しい情報でなければ、信頼性を担保することができないため、あなたの主張の根拠をはっきりと示すようにしましょう。(参考文献やデータの出典元など)
網羅性
網羅性については非常にシンプルです。
他のサイトで情報収集する必要がないぐらい、ユーザーの抱えている「悩み」、「質問」に対して、「網羅的に答え」を返している必要があります。
網羅性が欠如しているとあなたの記事だけでは、ユーザーの抱えている課題は解決しないため、ユーザーはあなたのサイトを離脱して、他のサイトを見に行ってしまいます。
そうすると、結果的にあなたの記事は高い評価を得られなくなってしまいます。
あなたが書いている記事のトピックに対して、網羅的な情報を提供するように心がけましょう。
読みやすく、分かりやすい文章を書くためのポイント
ここでは、Webライティングにおいて、読みやすく、分かりやすい文章を書くテクニックをご紹介します。
本記事では、初心者でも実践しやすい以下の3点について説明します。
- 感情表現をいれ、「自分ごと」と認識させて、「共感」を得る
- 「読みやすさ」、「分かりやすさ」にこだわる
- 冒頭で伝えたいことをまとめる
感情表現をいれ、「自分ごと」と認識させて、「共感」を得る
感情表現を用いることで共感を誘発し、自分ごとのように感じさ、ユーザーにコンテンツを読もうと思わせることができます。
読者が共感した文章は、読者にとって「自分ごと」になるため、「この文章は自分にとって関係があるな、じゃあ、読んだ方が良いな!」という心理になり、読み進めてもらいやすくなります。
読者に共感してもらうには、こちらから感情を伝えなくたはなりません。そのためには、どこが感情表現か分かりやすくすることが重要です。
どこが感情表現か分かりやすくする簡単なテクニックとして、以下の2点があげられます。
- 「」カギ括弧を用いてどこが感情表現か際立たせる
- 記号、絵文字などを用いる(!、?、♪など)
例えば、以下のような例が考えられます。カギ括弧を用いることで、話し言葉に見えるため、感情が伝わりやすくなります。
- 「記事を書いても成果がでずに困っている」
- 「数が多すぎて、どの旅館がいいか選びきれない」
記号を用いる例は以下のようなものが考えられます。
- 「美味しいものを食べると幸せな気持ちになりますよね♪」
- 「ブログで初めて広告収入が入って嬉しかった!」
「読みやすさ」、「分かりやすさ」にこだわる
「見やすさ」、「分かりやすさ」にこだわった記事を書くためには以下のテクニックが利用可能です。
- 改行と行間に気を配る
- 「漢字」と「ひらがな」をバランスよく使う
- 「この」、「その」、「あの」などの指示代名詞を減らす
- 箇条書きリストを利用して要点を整理する
- 情報を整理する(「目次」をつける)
- 文字サイズや強調に気を配る
- 写真やイラストを利用する
- マンガ的な演出をする
◆改行と行間に気を配る
直感的に読みたい、読みやすそうと思わせる記事を書くためには、改行と行間に気を配るようにしてください。
例えば、以下の例を見ていただくと、どちらが読みやすいかは明らかだと思います。
パターン①
SEOを成功させるWebライティングを行うためには、「ユーザーの利便性を最優先に考えること」が重要です。なぜなら、Googleの検索エンジンはユーザーの利便性を最優先した、ユーザーに価値のあるページを上位に表示するアルゴリズムになっているからです。ユーザーの利便性を最優先したコンテンツを作成するためには、ユーザーの「悩み」や「質問」に対して、「的確な答え」を返すコンテンツを作成するように心がけましょう。
パターン②
SEOを成功させるWebライティングを行うためには、「ユーザーの利便性を最優先に考えること」が重要です。
なぜなら、Googleの検索エンジンはユーザーの利便性を最優先した、ユーザーに価値のあるページを上位に表示するアルゴリズムになっているからです。
そのことは、Googleの経営理念からも明らかです。
ユーザーの利便性を最優先したコンテンツを作成するためには、ユーザーの「悩み」や「質問」に対して、「的確な答え」を返すコンテンツを作成するように心がけましょう。
「いかがでしょうか?」
極端な例ですが、明らかにパターン②の方が、読みやすいですよね!
このように改行、行間に配慮した記事を書くようにしましょう。
◆「漢字」と「ひらがな」をバランスよく使う
漢字の割合が多いとパッとみただけでも文章が難解に思われがちです。また、脳に対する負担も大きいので、漢字とひらがなのバランスには注意するようにしてください。
以下のような場合は、ひらがなを使うように工夫をしてみてください。
- ひらがなにした方が、読み手の負担が減りそうな場合
- 普段、感じで書かないような言葉を利用している場合
- 常用漢字に載っていない漢字
◆「この」、「その」、「あの」などの指示代名詞を減らす
ユーザーは、記事を最初から最後まで順番に読むとは限りません。
一部を読み飛ばして、自分が気になる箇所のみ読むというケースもよくあります。
その際、記事の途中から出てくる「この」、「その」、「あの」などの指示代名詞が何を指しているかわからず、記事の内容が正しく伝わらない可能性があります。
そのリスクを避けるために、並べく指示代名詞の利用はおさえて具体的に書くようにしましょう。
◆箇条書きリストを利用して要点を整理する
箇条書きリストを用いる方法も読みやすい記事を書く上でオススメの方法です。
箇条書きリストを使うことで、情報が整理されるため、「これを理解すればいいのだな」と読者の心理的な負担を減らすことができます。
箇条書きリストには数字付きリストと通常の「・」のリストがあります。
情報の総数が決まっている場合は数字付きリストを利用することで、より読みやすくなるでしょう。
以下は参考例です。
- 改行と行間に気を配る
- 「漢字」と「ひらがな」をバランスよく使う
- 「この」、「その」、「あの」などの指示代名詞を減らす
- 箇条書きリストを利用して要点を整理する
- 情報を整理する(「目次」をつける)
- 文字サイズや強調に気を配る
- 写真やイラストを利用する
- マンガ的な演出をする
- SEOとは何か
- SEOを成功させるためのWebライティングとな何か
- ブログ、Webサイトで成果を出すために、どのように文章を書けば良いか
◆情報を整理する(「目次」をつける)
長い記事であれば、どこに何が書かれているかが分かりづらくなります。
そこでオススメの方法はページの冒頭の方に「この記事にはどのような情報があるのか」を示す「目次」を配置することです。
冒頭に目次(ページ内リンク)にすれば、読み手は自分が欲しい情報まですぐにジャンプできるようになり、ユーザーの利便性が上がります。
ただ、ページの情報を上手く整理しないと目次の項目が多くなりすぎ、ユーザーの心理的負担が増えてしまいますので、注意が必要です。
◆文字サイズや強調に気を配る
文字サイズや強調表現に気を配ることも記事をみやすくする上で有効です。
以下のことを考慮すると良いと思います。
- 文字のフォントは見やすいか?
- 文字のサイズはちょうどいいか?
- 文字の強調には何らかのルールがあるか?
- 文字の色や背景とのコントラストはちょうど良いか?
例えば、色による強調を行うには、信号機のルールを用いて、以下のような配色ルールが考えられます。
| 色 | 強調の意味 |
| 赤 | 否定、禁止、ネガティブな強調 |
| 青 | 肯定 |
| 緑 | 例示、用語の強調 |
| オレンジ | 単純な強調 |
◆写真やイラストを利用する
記事の中で取り上げるテーマや内容によっては、文章だけではなく、写真やイラストを利用した方が良い場合があります。
記事のなかに写真や図、イラストが入っていると直感的に理解しやすくなり、ユーザーの負担を減らすことができます。
文章だけで表現するのが、困難だと感じた場合は、積極的に写真やイラストの利用を検討しましょう。
◆マンガ的な演出をする
マンガを読みづらいと感じる方はおそらくいないのではないでしょうか?
マンガはもっとも「分かりやすさ」を追求したコンテンツですので、その手法を上手く利用することも有効な手段といえます。
WordPressを利用したブログでも、吹き出しによる会話調の表現を用いることで、マンガのようなテイストを演出することが可能です。


冒頭で伝えたいことをまとめる
こちらはぜひとも実践していただきたいテクニックです。
Webサイトに掲載する文章では、まず「最初に結論を伝える」ことが重要です。
結論を先に伝えることで、「なぜそういう結論になるの?」と読者が理由を知りたくなります。
この順序が逆転してしまうと、とたんにそのコンテンツは読まれなくなってしまいます。
なぜなら、Webサイトを訪れるユーザーはその記事に自分の求める「答え」がないと思うとサイトから離脱してしまうからです。
記事を読み進めていくと、とても重要なことが書かれているのに、冒頭を読んだだけで、ユーザーが離れてしまうのは非常にもったいないことです。
ですので、あなたのコンテンツでは、まず最初に「最初に結論を伝える」ことを心がけてください。
USPを伝える
USPとはUnique Selling Propotisionの略で、「他にはない独自の強み」のことです。
あなたが何か商品を売りたいときは、その商品のUSPを伝えることは非常に大切です。
なぜなら、「USPを伝えることは競合商品との比較ポイントを伝えること」になるからです。
ユーザーが商品やサービスを選ぶ際、多くの場合はそれぞれの商品を比較します。
そのため、比較ポイントがはっきりしたUSPを打ち出すことが、大きなアピールに繋がります。
また、USPをはっきりさせることで「いろいろなWebサイトやブログで紹介されやすくなる」といったメリットや「デザインの方向性やコンテンツの方向性がブレなくなる」というメリットもあります。
それでは、参考書籍のストーリーを例に旅館のUSPについて考えてみましょう。
| ハード面 | ソフト面 |
| 温泉の種類と質 | 料理の種類と質 |
| 施設 | 接客の質 |
| 部屋の品質、広さ | 主人や女将の個性 |
| 景観 | 歴史 |
| 立地 | 宿泊プランなど |
注意すべき点は、どこの旅館でも打ち出せるような強みをUSPにしてはいけないということです。
例えば、「老舗である」とか「料理がおいしい」などがこれにあたります。
どこの旅館でも料理がおいしいことを強みとしているでしょうし、よほど個性的な料理長がいたり、ミュシュランで星を取得していたりしない限り、他社と差別化できるUSPにはなりません。
USPを考えるポイントは、以下の2点を軸に考えることです。
- 競合に真似されにくいこと
- 競合と同じステージで闘わずにすむこと
参考書籍で主人公たちは、「親孝行プラン」という独自のプランを打ち出し、USPとしています。
早くに両親を亡くし、旅館を切り盛りする若い二人が、親孝行したくてもできなかったという思いで考えたからこそ成立したUSPです。
詳しくは、「沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—」をご覧ください。
「カップル向けプラン」などに力を入れている競合の旅館はたくさんあると思われますが、「親孝行プラン」となればオリジナリティがあり、競合と真っ向から闘わなくてすみます。
まとめ
今回は「SEOを成功させる、初心者のためのWebライティング」ということで、初心者でも実践できるWebライティングのテクニックについて解説させていただきました。
「いかがでしたでしょうか?」
意外にすぐにでも実践できそうなテクニックが多かったのではないでしょうか。
最後にもう一度、本記事の要点を説明しておきます。
ブログやWebサイトで成果をあげるには、Googleから評価される記事を書く必要があります。
そのためには、SEOを意識した記事を書く必要がありましたね。
SEOを意識した記事を書くために以下のポイントを意識するようにしてください。
- 専門性、信頼性、網羅性の3つの要素を意識して記事を書く
- 読みやすく、分かりやすい文章を書くためのポイントをおさえて書く
- USPをわかりやすく伝える
今回、参考書籍とさせていただいた「沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—」は、ストーリー仕立てで非常に分かりやすくWebライティングの手法がまとめられています。
本記事を読んで、興味を持たれた方は、実際に手にとってご確認いただけたらと思います。
本記事が、少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。
多くの読者に価値のあるコンテンツを届けられるように一緒に頑張っていきましょう。